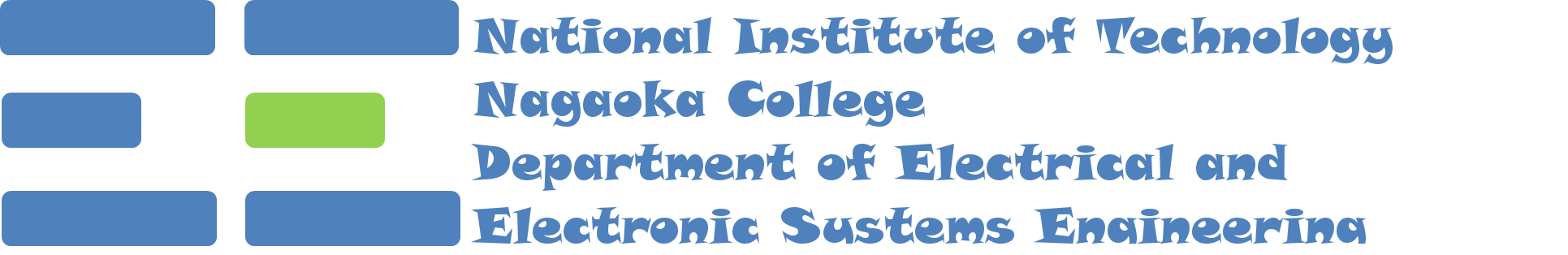初めての電子顕微鏡

"電子顕微鏡"は、肉眼や普通の顕微鏡では見えないような小さな物をみることができたり、
どんな元素が含まれているのかなどのいろんな情報を知ることができます。
電子デバイス・半導体や各種材料の研究開発や品質管理では非常によく使われる分析手法です。
本日は、材料分野の卒業研究を今後始める電気電子システム工学科4年生の6人が、
はじめて電子顕微鏡の操作に挑戦してみました。
しかも、遠隔地においてある電子顕微鏡の操作です。
長岡技術科学大学に設置されている日本電子社製JCM-7000という電子顕微鏡を
長岡高専の電子通信実験室からテレビモニタを通して手元のマウスで操作することができます。
信濃川を挟んで東西に位置する両機関の間の距離は、およそ12km。
遠隔と呼ぶには近い距離かもしれませんが、インターネットを介した操作ですので、海外からも操作することができます。
この遠隔操作による分析設備の利用環境は、長岡技術科学大学が中心となったコアファシリティネットワーク事業において整備されました。
本日のワークショップでは、日本電子株式会社の野村様から電子顕微鏡の講義をしていただき、
その次に長岡技術科学大学の古野様と江村様のサポートにより、実際に電子顕微鏡を操作してみました。
様々な試料を観察し、自分で見たい場所を拡大、フォーカスをあわせてみる・・・・
拡大するとこんな風に見えるのか!こんな元素が含まれていたのか!いろんな発見がありました。
また、原理を知ったうえでデータを見なければ、事実を間違って解釈してしまうということも教わりました。
装置は使って経験してみなければ、ノウハウが蓄積されていきません。
電子顕微鏡は長岡高専にも設置されており、これから研究に本格的に取り組む4年生もたくさん使うことになります。
沢山の経験を積んで、様々な産業に応用できる分析スキルを身につけていってくれるといいなと思います。